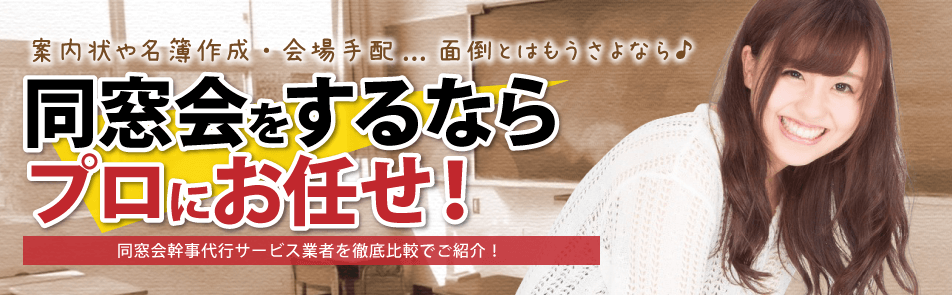
同窓会の幹事はいつ頃から準備を始めるべき?具体的な手順も知ろう!

同窓会を開催するにあたり、幹事はなくてはならない存在です。参加者に楽しい時間を過ごしてもらうためにも、予想外のトラブルに遭わないためにも、具体的な準備手順や時期をしっておくことが大切といえるでしょう。ここでは、幹事として知っておきたいポイントを紹介するので、参考にしてください。
同窓会はいつ頃開催する?
同窓会は、基本的にオールシーズン開催されます。とはいえ、参加しやすい時期や参加しにくい時期というものがあるようです。いつ頃、開催するとよいかを解説します。
■同窓会を行う、おすすめのシーズン
同窓会を開催するには参加人数を揃える必要があります。そのため、地元に帰省している可能性が高い時期に開催するとよいといえるでしょう。たとえば、お盆の時期や、年末年始があげられます。一方で、3月・4月は、会社の決算時期であることが多いようです。そのため、その時期の開催は参加率が低いとも考えられています。
■同窓会を行う、おすすめの日程
同窓会の翌日が休日である日にちがおすすめです。すべての人が休日であるとはいえませんが、翌日が平日であれば参加率が低い傾向にあるでしょう。また、大型連休・長期休暇の時期は、家の行事があることも考えられます。できるだけ早く案内状を出すとよいでしょう。
■同窓会を行う、おすすめの時間帯
仕事が終わると想定される18時から19時以降に開始するケースが多いようです。また、大型連休・長期休暇の時期であれば、日中の開催も検討してよいでしょう。会場の予約を行うためにも、早めの行動がカギといえます。
同窓会を行う頻度
同窓会を行う頻度には、とくに決まりがないとされています。連絡がとれる人数や、同窓会を行おうとする発起人がいるかどうかで大きく変わるといえるでしょう。同窓会は必ずしも行わなければいけないものではありません。参加希望者の人数や、発起人の意思で検討すると考えることをおすすめします。
同窓会の幹事はいつ頃から準備を始めるべき?
同窓会を開催するにあたって、準備しておくことは複数あります。また、人数が多ければ多いほど準備に時間が必要といえるでしょう。つづいて、同窓会の幹事となった場合に準備を開始しておきたい時期と、その準備内容を解説します。
■半年前ごろ
同窓会の計画を立てる
中規模の同窓会であれば1人で準備できるかもしれませんが、人数が多い場合は複数人に依頼するとよいでしょう。決まりはありませんが、1つのクラスであれば2名程度の幹事がいるとスムーズに進められる傾向にあるようです。幹事が集まれば、開催日時や会場について検討していきます。会費予算や先生を招待するかなど、具体的に決めましょう。
■4か月前ごろ
予約や案内状の作成
予算や日時にあわせてより具体的な会場を決め、仮予約を行います。同窓会や忘年会に人気の時期での開催であれば、予約が困難なケースも。はやめに会場を押さえておくとよいでしょう。会場が決まれば、会費を決定できます。案内状に記載すべき内容をすべて確定していきましょう。
また、送付先のリストも作成しておきます。住所が分からない人がいることも考えられるため、早めに作成しておくことをおすすめします。
■3か月前ごろ
案内状の送付
作成した案内状を発送しましょう。遅くとも、3か月前に発送しておくとよいでしょう。この際、出欠の回答期日を設けることが大切です。回答期日は、開催日の1か月以上前に設定しておくことで、回答がない人への問い合わせをする時間を確保できます。
■2か月前ごろ
同窓会のプログラム検討
もし先生を招待する場合は、先生への贈り物を検討・購入したりするケースも。場合によってはビンゴゲームや、タイムカプセルの披露といったイベントを盛り込むとよいでしょう。その際、司会進行役を決めておくことや、時間割も考えることで円滑に進めることができます。
■1か月前ごろ
会場の最終予約確認や二次会の手配
出欠の回答が集まり始めるため、会場に人数の確定を行います。会場によっては、急な人数変更を行うとキャンセル料が発生することも。会場と参加者に、慎重に確認する必要があるといえます。また、二次会の手配を行うこともおすすめです。二次会の参加者は当日になってみないとわからないことが多いため、席だけを予約するなど臨機応変に対応できるようにしましょう。
まとめ
人数が多ければ多いほど、同窓会開催に向けての準備に時間がかかるものです。早めの準備が大切とはいえ、開催準備を行う適切な時期というものがあります。抜けなく適切に準備を進めることで、参加者も幹事も安心して同窓会を楽しむことができるでしょう。紹介した手順を参考に、ぜひ楽しい同窓会にしてくださいね。












