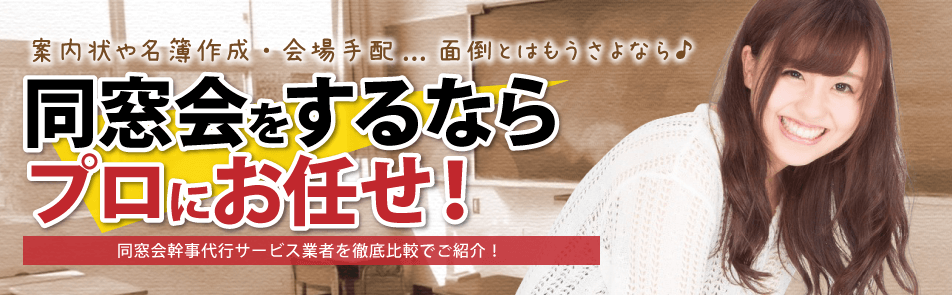
事前準備が大切。同窓会開催までの幹事のスケジュールを把握しよう!

幹事は、企画、準備、同窓会当日、その後の対応まで、すべてに関わる存在です。そのため、同窓会全体のスケジュールを把握しなければいけません。大切なのは早めに準備して、調整役として動くことです。この記事では、参加者全員が楽しめる同窓会を開催するために、幹事のスケジュールを解説します。同窓会を控えている人は参考にしてください。
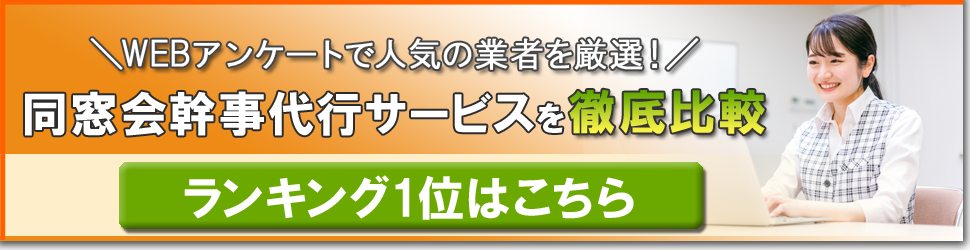
同窓会開催までの幹事のスケジュールを把握しよう!
同窓会を開催するためには、3~6ヶ月の準備期間が必要です。これは、学校の所在地やクラスの人数によっても異なりますが、遠方に住んでいる人の出席を期待するのであれば、準備期間を長めに設定しましょう。
■開催日の6ヶ月前
まず、幹事に協力してくれるメンバーを探しましょう。幹事はできないという人でも、同窓会の開催を期待している人はいるものです。積極的に声をかけてください。中心メンバーが決まった後は、互いに連絡を取りながら事前準備を進めましょう。
■開催日の5~4ヶ月前
幹事をリーダーとして、メンバーと一緒に「開催日の検討」「名簿作成」「会場の検討」「会費の設定」などを行います。決定すべき内容が多いため、幹事は調整役として忙しくなるでしょう。
■開催日の3ヶ月前
ある程度参加者の人数を把握できたところで会場を決めます。人数が多いと、近くの居酒屋というわけにはいきません。ホテルやレストランなど、知名度や人気のある会場を選ぶことになるため、3ヶ月以上前には予約します。案内状の発送や会場の下見などは、メンバーに協力してもらいましょう。
■開催日の2~1ヶ月前
出席の確認を行い、会場側と打ち合わせを重ね、当日のプログラムを決めます。一次会だけでは物足りないという人のために、二次会の予約を行ってください。二次会は席だけの予約で済ませ、食事は各自で注文といった形にするとよいでしょう。
■開催日2週間前
幹事は、当日協力してくれるメンバー向けに、役割分担表や進行表を作成します。「いつ」「誰が」「何をするのか」を記載して、頭の中に入れましょう。
同窓会当日にやること
同窓会当日、幹事はやるべきことが多くある物です。メンバーをまとめるリーダーとして、段取りよく進めていきましょう。
■会場到着
幹事やメンバーは、同窓会の2時間前には集合するとよさそうです。幹事は、役割分担表や進行表をもとに、メンバーの動きを確認していきます。
■会場準備
「受付のセッティング」「座席の名札の設置」「贈り物の準備」「リハーサル」など、同窓会がスムーズに進行するように会場を整えましょう。
■受付
メンバーは、各自の持ち場にスタンバイし、受付をスタートさせます。幹事は集まり具合を見ながら、スピーチする人や恩師を確認し、一声かけておくとよいでしょう。
■同窓会の開始
幹事は司会者に指示を出しながら、スピーチや余興などを進めます。全体の様子を見ながら、一部だけが盛り上がらないということがないように、席を入れ替えたりゲームをしたりするなど工夫しましょう。
■同窓会の終了
同窓会の終了間際で慌てないように、時間配分に注意しましょう。時間がオーバーしているときは、歓談や食事を通して時間の調整を行います。幹事は、その間に各メンバーから領収書を受取り、会計処理を済ませてください。その後は二次会へのアナウンスを促し、スムーズに移動できるようにしましょう。
同窓会が終わった後にやること
同窓会を単なる飲み会で終わらせないために、幹事には同窓会が終わった後もやるべきことがあります。
■メンバーへのお礼
協力メンバーに、メールやSNSでやり取りをして感謝の気持ちを伝えましょう。大変だったことなどを振り返ると、次の同窓会開催へつながるかもしれません。
■恩師へ手紙を郵送
恩師を招いた場合は、お礼の手紙を書きましょう。当日撮影した写真を同封すると喜ばれます。
幹事というと、堅苦しく忙しいイメージがあります。事前準備や打ち合わせなどは欠かせず、時間を費やすことになるでしょう。しかし、同窓会には進行やプログラムに特別なルールがありません。参加者が楽しんでいれば、大成功なのです。そのため、幹事は同窓会のプロデューサーとして、余裕のあるスケジュールを組み、メンバーに協力してもらうとよいでしょう。チームとして動くと、幹事自身の負担が軽くなります。また、新しい人脈づくりにもつながるでしょう。












