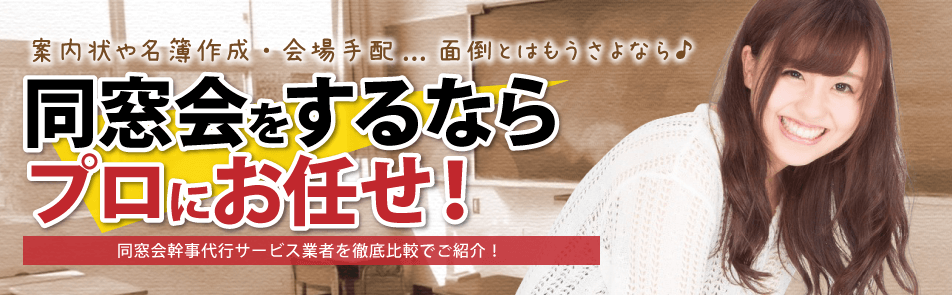
同窓会の幹事は誰がやる?幹事の決め方をご紹介!

学生時代の仲間と交流できる貴重な機会である同窓会は、当然ですが幹事の企画があって実現するものです。しかし、同窓会の幹事は誰がやるのか、どのように決めるのか疑問に思ったことはありませんか?今回は、同窓会の幹事は誰がやるのかといったことや、幹事の決め方、向いている人の特徴に加え、幹事がやるべき準備について詳しく解説します!
同窓会の幹事は誰がやるべき?
同窓会の幹事をやる人には特別な決まりはなく、基本的には引き受けてくれる人にお願いすればOKです。しかし、大人数で集まる同窓会は準備にかなりの手間と時間がかかります。そのため、「面倒な仕事を引き受けたくない」という思いから、同窓会の幹事を嫌がる人も少なくありません。
「同窓会をやろう」と声を上げるのはクラスの中心人物や学級委員などであることが多いですが、逆にいえば誰も声を上げなければ同窓会は開催されません。学校によっては、誰も幹事を引き受けずに結局同窓会が開催されなかったという事態を防ぐため、卒業する際に同窓会幹事を決めておくケースもあります。
同窓会の幹事の決め方
同窓会の幹事は、「同窓会をやろう!」と思い立った人が幹事となります。しかし、1人で同窓会の企画を進めるのはかなり大変であるため、多くの場合は複数人で幹事の仕事を引き受けるのです。ここでは、幹事の決め方として、幹事にふさわしい人の特徴を解説します。
報連相ができる人
複数人で幹事をするといってもそれぞれ家庭や仕事があるため、基本的には会って計画をする機会はほとんどないと考えてよいでしょう。アプリのグループトークなどを利用して連絡を取りながら企画を進めることになるため、報連相をしっかりできることが幹事の最低条件となります。
最後まで責任を持って取り組める人
同窓会の幹事はやることが多いうえ、思うように進まない場面も多々あるでしょう。「候補にしていたお店の予約がどこも取れなかった」「想定よりも参加者が集まらなかった」といったことが起こると、これまでの労力が無駄になったような気持ちになる人も少なくありません。しかし、開催の声を上げて参加者がいる以上、途中で企画を投げ出すことはできないもの。うまくいかないことがあっても、最後まで責任を持って取り組まなければなりません。
参加対象者と連絡が取れる人
学年やクラスの仲間を集める際、当時の住所から引っ越している人と連絡が取れないというトラブルは多いです。しかし、最近ではSNSなどでつながる機会も多いため、住所が分からない場合でも連絡をしやすくなっています。クラスの中心人物や部活動のキャプテンなど、できるだけ多くの人とつながっている人物が幹事となることで、スムーズに参加者への連絡が取れるでしょう。
同窓会の幹事がやるべきこと
ここまで同窓会幹事の決め方や向いている人の特徴を解説しましたが、実際の幹事の仕事にはどのようなものがあるのでしょうか?ここでは、同窓会の幹事がやるべきことを3つご紹介します。
日付の決定と参加確認
同窓会の開催を決めたら、まずは日付の決定と参加確認を行います。会場予約のことも考え、余裕を持った日取りにしておきましょう。参加者をリストアップしたら、案内ハガキの郵送やSNSなどを利用して出欠を確定します。日付は帰省が多いお盆や正月、ゴールデンウィークがおすすめです。
会場予約
参加人数が把握できたら、会場を予約しましょう。30人以下であれば居酒屋やレストランでの着席形式、大人数の場合はホテルや結婚式場での立食形式が向いています。
当日の会費計算、乾杯など
同窓会当日を迎えたら、参加者からの会費集め、開会のスピーチや乾杯の音頭などを担当します。また、担任教師を招待する場合は、スピーチの依頼をするのも幹事の仕事です。
まとめ
今回は、同窓会の幹事の決め方や向いている人の特徴、同窓会の幹事がやるべきことについて詳しく解説しました。同窓会の幹事は「同窓会をやりたい!」と思った人が引き受けるものですが、多くの場合はクラスの中心人物や学級委員、卒業時に決められた同窓会委員などが担います。幹事の仕事は複数人で引き受けることが多いため、幹事・副幹事を依頼する際には、報連相がしっかりとできる人、最後まで責任を持って取り組める人にお願いしましょう。また、幹事の仕事には、日付の決定や参加確認、会場予約などがあります。同窓会を開きたい人、幹事を依頼された人は、今回の記事を参考にしてみてください!











