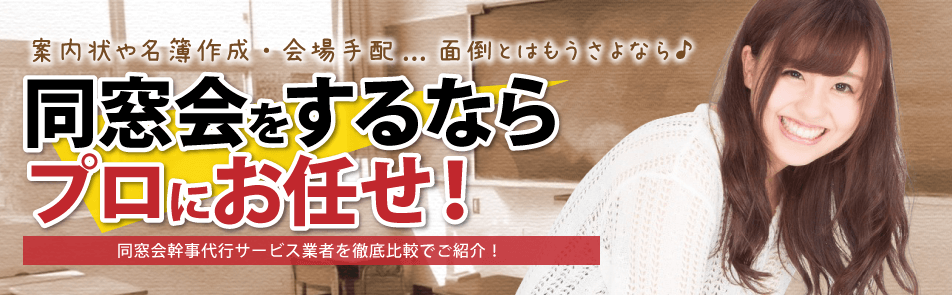
開催時期が意外と大切!同窓会のタイミングはいつ頃が最適?
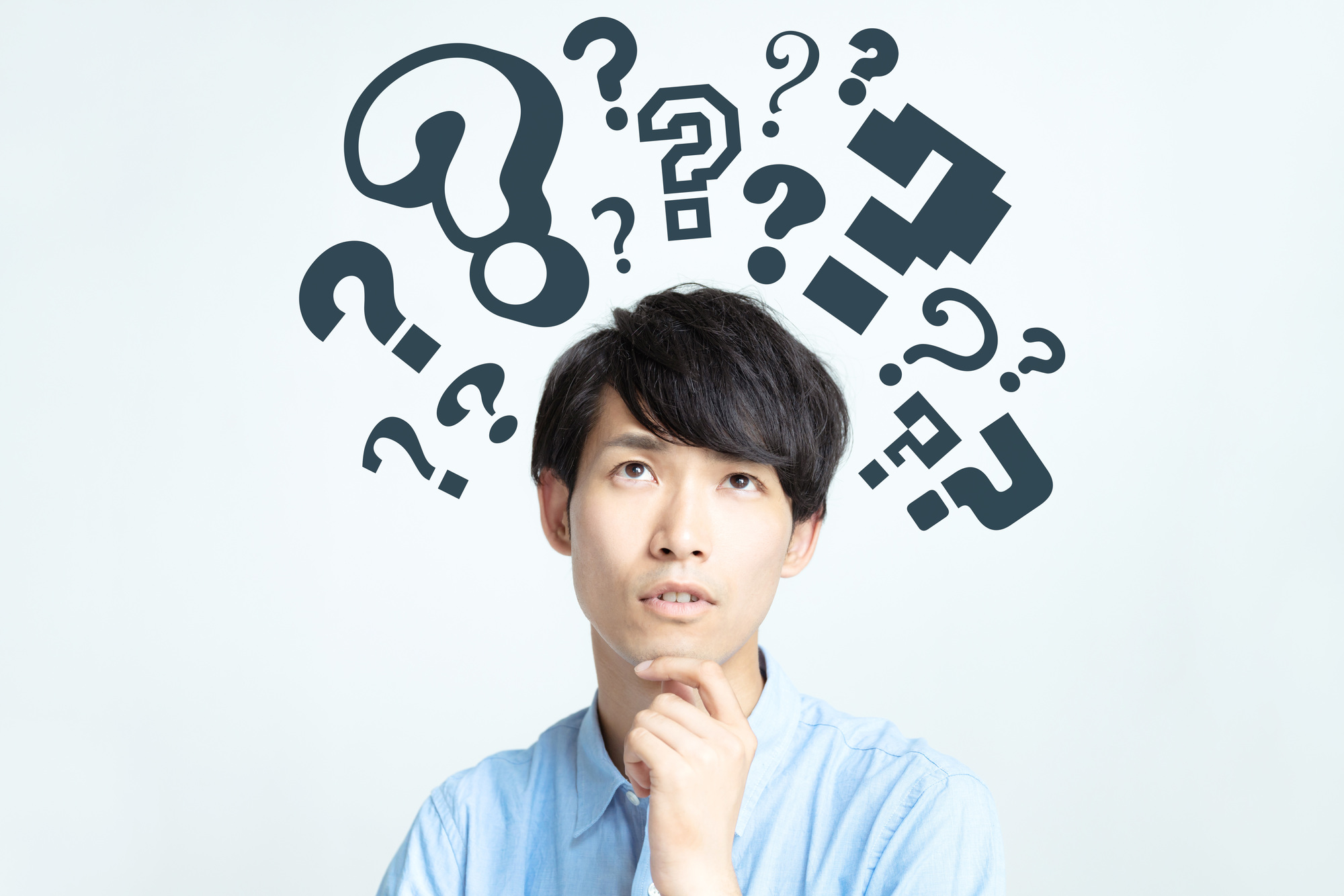
若いときは実感しづらいのが「友人の大切さ」です。ある程度、年齢を重ねると人付き合いは広くなりますが、本当の友人と呼べる存在を作るのはなかなか難しいでしょう。だからこそ、同窓会では多くの友人に会いたいものです。では、どうしたら同窓会の出席者をたくさん集められるのでしょうか。今回は、同窓会のタイミングについて説明します。
同窓会のタイミングはいつ頃が最適?
同窓会の開催日時は、先に決めておかなければなりません。ほとんどの場合、主催者は3~6ヶ月前には開催日時を決め、準備を始めるものです。ただ、地域性や年代によって同窓会のタイミングは異なるでしょう。
首都圏や都心部で同窓会を開催するのであれば「週末」にしましょう。これは、交通の便がよく、会場に行きやすいからです。土曜日や日曜日が最適です。
地方で同窓会を開催するのであれば、お盆やお正月などの「大型連休」にしましょう。その方が、家族を連れて帰省するタイミングで同窓会に参加できます。ただし、ゴールデンウィークは要注意です。この時期は、新年度で仕事が忙しく、人事異動も多いため、働き盛りの30代や40代の場合、出席できないかもしれません。
同窓会の頻度はどれくらいがいい?
同窓会で友人と話していると、学生時代にタイムスリップして会話が盛り上がり「あっ」という間に時間が過ぎるものです。なかには、同窓会が終わった後、「もう少し話したい」「物足りない」と感じる方もいるでしょう。実際、同窓会の時間は、一次会と二次会を合計して4時間程度です。
もし時間をオーバーしてしまうと、会場側から追加料金を請求される恐れがあるため、時間通りに終了させなければいけません。では、次の同窓会はいつ開催すればいいのでしょうか。ここからは同窓会の頻度について考えましょう。
■1度も同窓会がない
「同窓会に1度も参加したことがない」という方も多いでしょう。そもそも同窓会は、「開催しよう」という主催者がいないとできません。また、友人同士の連絡状況、小学校や中学校の地域性などにより開催できるかどうかが決まります。
■年に1回程度、数年おきの開催
最初の同窓会をきっかけに新しい人間関係が生まれ、次の同窓会につながるケースがあります。また、今回は欠席したけれど、次回は参加したいという前向きな返答があるケースもあります。どちらにしても、次回の同窓会に賛同してくれる人が多いのなら、年に1回や数年おきに開催するのもいいでしょう。
■同窓会の頻度は主催者側の状況で決まる
結局のところ、同窓会の頻度は主催者側の状況によります。主催者側は、案内状を出したり会場を予約したり負担が大きいからです。楽しみながらできるように、無理のない開催頻度にしましょう。
同窓会の手順を確認しよう!
同窓会は、企画から当日までフリースタイルです。ただ、ある程度、同窓会の手順を知っておかなければ開催できません。ここからは、同窓会の基本的な手順を説明します。
・開催日と会場の設定
まず、決めるのが開催日です。地域性や規模によっても異なりますが、6ヶ月ほど前から準備を始めるといいでしょう。
・案内状の作成
卒業アルバムに名簿がある場合は、その住所に案内状を郵送し、出席者の確認を取ります。しかし、最近は名簿のない学校が多く、個人情報保護法によって連絡先がわからないケースがほとんどです。友人を頼ったりSNSを活用したりして、出席者を募りましょう。同窓会のために、ホームページを立ち上げるのも便利な方法です。
・会場側との調整
出席者のおおよその人数を会場側に伝えます。会場の広さや食事などを調整しましょう。その後、会場の場所や会費などを決めて、正式な案内状を出席者に出します。
・主催者側の調整
幹事がリーダーとなり、司会係、受付係、会計係など役割分担をしていきます。受付や司会は、交代制にして、それぞれの自由時間も確保しましょう。
・開催日当日
幹事や司会などの主催者側は、早めに会場に入り、リハーサルなど最終調整を行います。
多くの友人の意見を取り入れても、タイミングをいくら調整しても、同窓会には欠席者が必ず出てしまいます。仕事、子育て、介護などそれぞれに事情があり出席したくてもできない人がいるからです。また、同窓会に対して、好意的に思っていない人もいます。結局、幹事を引き受けた人や、受付係や会計係など主催者側のスケジュールに合わせ、同窓会の日程を決めるのがいいでしょう。その方が、同窓会に向けて余裕を持って行動できます。












