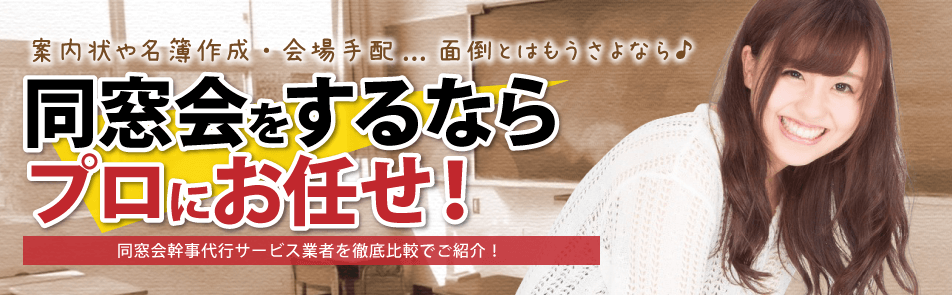
同窓会の案内状を出す際の注意点とは?具体的な作成手順も解説!

同窓会の幹事としてやらなければいけないのが「案内状」の作成です。出欠席の確認のためにも案内状を作成し、同窓生に送らなければいけません。もっともどのように案内状を作ればよいのかわからないという方も多いと思うので、今回は同窓会の案内状を出す際の注意点や作成手順について詳しく解説していきます。
同窓会の案内状を送るメリット・デメリット
同窓会の案内状を作成して送ることは、メリット・デメリットがあります。それぞれ具体的にどういった内容なのか詳しく見ていきましょう。
■同窓会の案内状を送るメリット
同窓会の案内状を送るメリットとしては、以下の通りです。
・出欠席を簡単に確認できる
・具体的な人数を事前に確認できる
・先生など年配の人にも連絡を取りやすい
同窓会の案内状を作成して送ることによって出欠席を簡単に確認できるので、どのくらいの人数が集まるのか事前に把握できます。また、SNSなどを利用していない年配の先生達にも同窓会の連絡を取りやすい、というのも大きなメリットです。
■同窓会の案内状を送るデメリット
同窓会の案内状を送るデメリットとしては、以下のようなことが考えられます。
・案内状の費用がかかる
・作成の手間がかかる
・確認に時間がかかる
案内状を作成するにははがきや手紙などを何枚も作る必要があるため、手間とお金がかかってしまいます。また、SNSなどとは異なり時間がかかってしまうので、同窓会までにそこまで余裕がない場合には、準備などでかなりバタバタしてしまう可能性があるでしょう。
同窓会の案内状の作成手順
同窓会の案内状を作成するにあたっては、以下のような手順で行うと効率的に進めることができます。
・同窓生のリストを作る
・案内状のタイプを選ぶ(はがき・手紙など)
・案内状の内容を決める
・デザインを考える
・招待する先生の会費などを決める
同窓生のリストを作ってから案内状の制作を進めると、かなり効率的に進行できます。また、案内状のタイプや内容などもしっかり決めてから中身を制作すると、そこまで時間もかかりません。イラストや内容などはテンプレートなどを活用すると、1から考える必要もないのでおすすめです。
一点注意したいのは、招待する先生についてです。先生に関しては案内状も別途制作し、会費なども分担して負担するようにしましょう。
同窓会の案内状を出す際に注意するべき点
同窓会の案内状を出す際には、以下の点に注意してください。
・案内状を出すタイミング
・封筒の入れ方
・メールで案内をする場合
それぞれ順番に詳しく解説していきます。
■案内状を出すタイミング
案内状出すタイミングについては、遅くとも開催日から2か月前には送るようにしましょう。出欠席の返事を前もってもらうためにあることはもちろんのこと、参加する人の日程調整なども必要になってくるからです。人数の確定も早く決まれば決まるほどよいので、案内状の作成から送付まではできるだけ早めに行っておくとよいでしょう。
■封筒の入れ方
案内状によっては封筒に入れて送付するという場合もあります。同窓会の案内状を送るにあたって、封筒の入れ方については決まった形式というものは存在しません。そのため手紙などを送る際の一般的なマナーを抑えて送るとよいでしょう。
■メールで案内をする場合
近年ではSNSやメールで案内をするということも珍しくありません。とくに卒業アルバムなどに個人情報を載せることが厳しくなってきたことから、住所や電話番号などがわからないという場合も多いでしょう。もっともメールやSNSの場合、送り間違いや確認漏れなどが起きやすいため、しっかり管理しておくことをおすすめします。
同窓会の案内状については、調べればテンプレートなども多いためすぐに作成できます。案内状を早めに作成して、出欠席の確認をできればスムーズに同窓会を開催できます。なるべく早め早めに行動するのがよいでしょう。












